最初に伝えたいこと
・管理とは「目の前の現場」ではなく「チームの意思疎通」に尽きる。
・リーダーは“自分でやる人”ではなく“みんなを動かす人”。
・そのためには、現場との関係性がすべての土台になる。
こんなとき、ありませんか?
「ちゃんと指示したはずなのに、現場が動いていない」
「報告を受けても、“見えてる世界”が違う気がする」
「部下に言っても、理解されていない気がして、結局自分で動いてしまう」
これ、全部「チーム内の認識ズレ」が原因かもしれません。
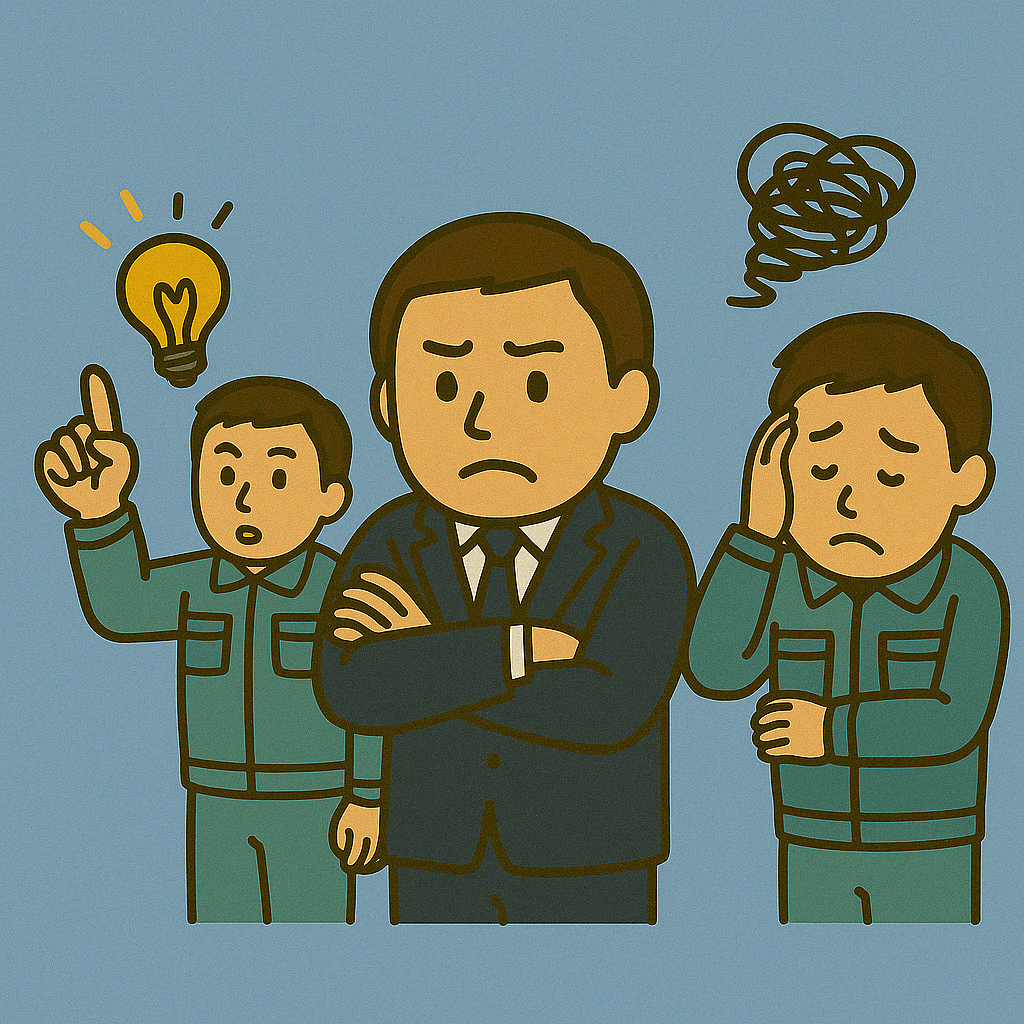
この記事で得られること
・「自分でやらなきゃ」から「みんなでやる」への視点転換
・現場との意思疎通が変わると、指示も報告も伝わり方が変わる
・管理職が“楽になる”のは、孤独に戦わなくなったときです
私の経験を基にご説明します
こんにちは。ブログ管理人のケイです。
今日は「管理=コミュニケーション」だと痛感した、あるエピソードを紹介します。
私が製造部のチームリーダーになったばかりの頃、どうしても納得いかない出来事がありました。
午前の会議で確かに「Aラインの改善は今日中に着手」と伝えた。
でも夕方になって見に行くと、ラインはいつも通り動いていて、誰も改善の準備をしていなかったんです。
「おかしい、伝えたのに…」
モヤモヤしながら副リーダーに聞くと、こんな返事が返ってきました。
「あ、あれって“検討始めておいて”って意味かと…」
このとき、心から思いました。
「同じ言葉でも、受け取り方がこんなに違うのか」と。
実はこのすれ違い、今回が初めてではありませんでした。
日々の業務報告も「なんかズレてる」と感じることが多く、
そのたびに私は「だったら自分でやったほうが早い」と背負い込んでしまっていたんです。
でも、それがダメだった。
部下を“動かす力”がないまま、自分で全部やるのは、リーダーではなくただのオペレーターなんですよね。
それから私は、以下のことを徹底するようにしました:
- ・指示を出すときは「やること・目的・期限」を明確に
- ・報告を受けたら、「自分の目で確認する」プロセスを持つ
- ・現場の反応が鈍いときは、責める前に「なぜ伝わってないか」を考える
何よりも意識したのは、チームとの“対話”の質を上げることです。
上から押しつけるのではなく、共に状況を理解し、共に方針を決めていく。
それができたとき、ようやく「任せられる」チームになりました。
実際に現場の副リーダーからも、ある日こんな言葉をもらいました。
「最近、ケイさんが言うこと、すごく“伝わる”ようになりました」
それを聞いて私は思いました。
「自分が変われば、チームも変わる」んだと。
明日から使えるワンポイント
“伝えたつもり”じゃなく、“伝わったか”で判断する。
そのひと手間が、チームの推進力になります。
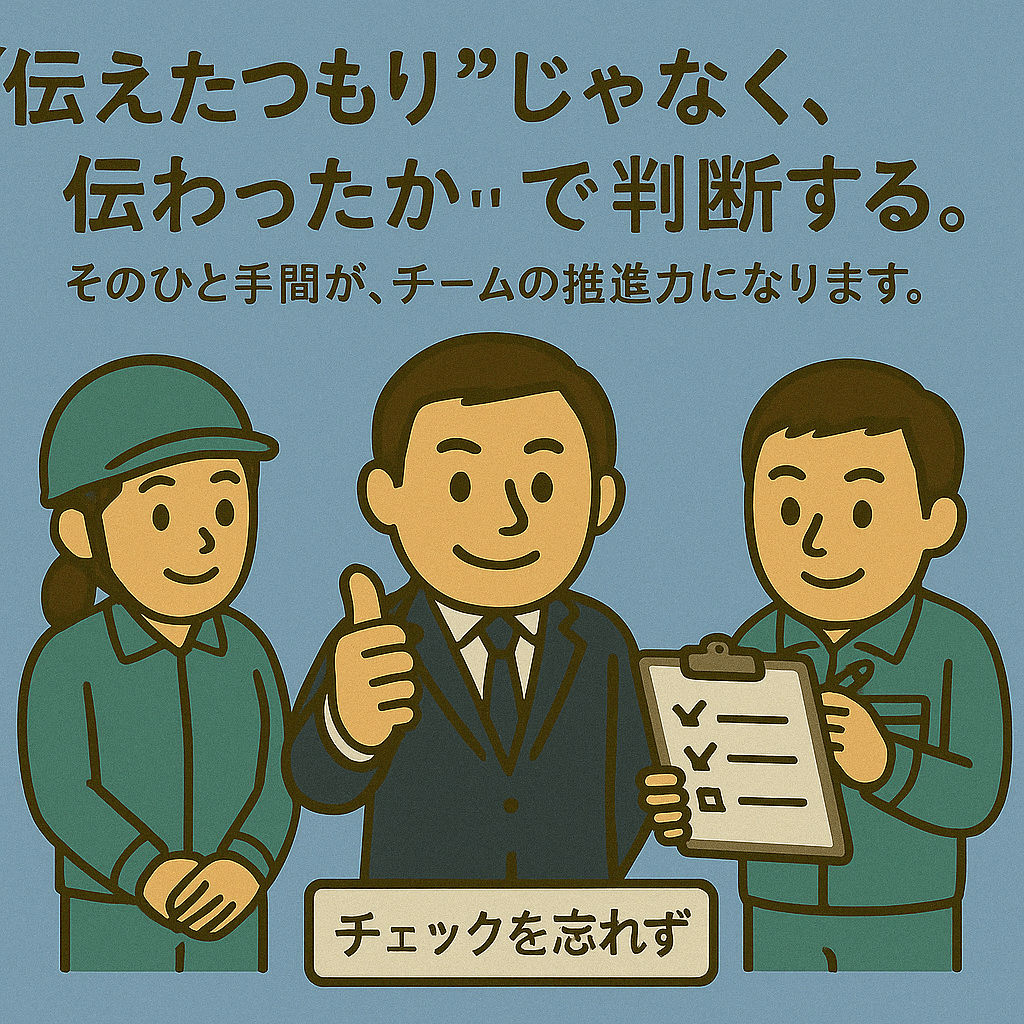
あなたの話も、聞かせてください
あなたの職場での悩みや気づきも、ぜひコメントやDMで教えてください。
このブログでは、リアルな現場の声を大切にしたいと思っています。




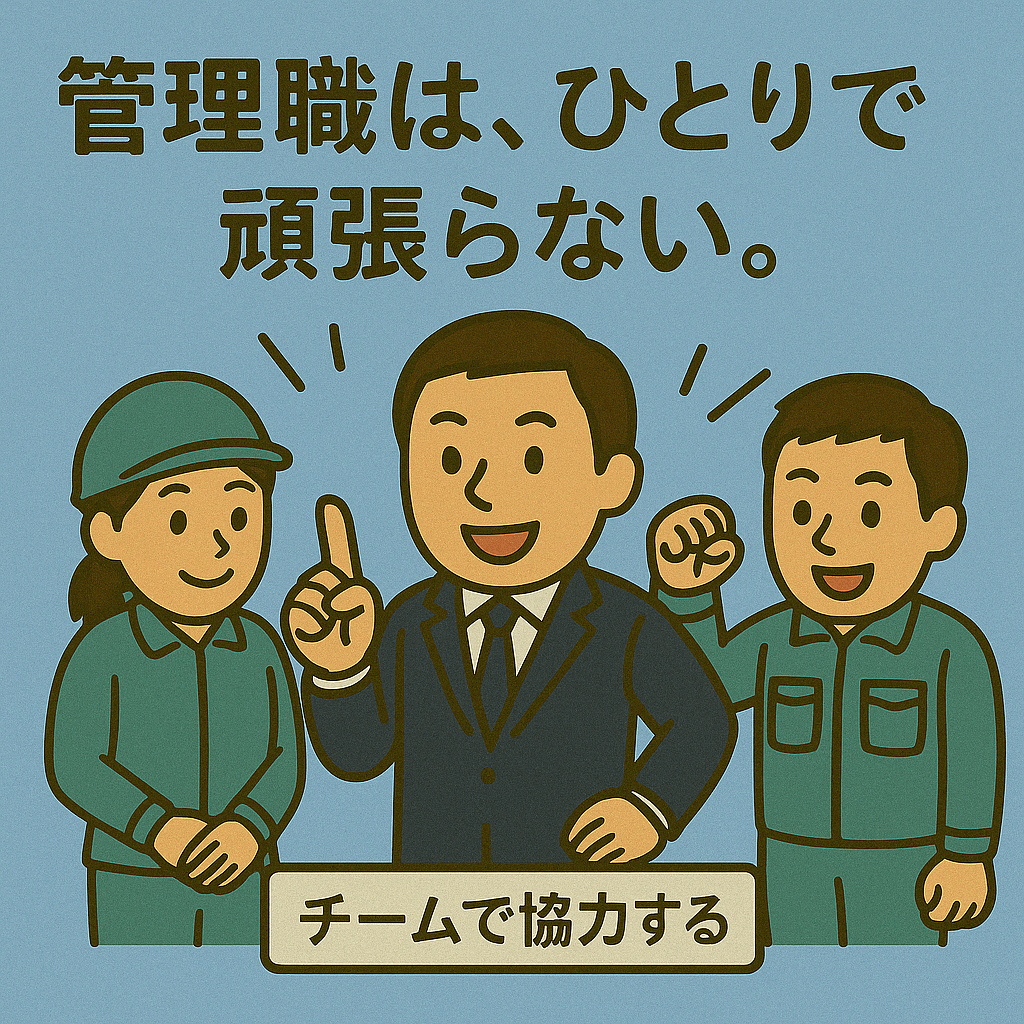
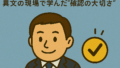

コメント